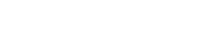蒼龍山 松源寺

当寺は麹町四番町に創建されたが、年代は不詳。慶長18年に牛込神楽坂に移り、明治41年に再び現在の地に移転している。
当時は通称〝さる寺〟と呼ばれ、さる寺縁起として『江戸名所図会』に「昔、境内に猿をつなぎて置きたりとて、今も世に猿寺と号く」と記されている。
また、元禄の頃四代目の住職・徳門和尚が渡船に乗ろうとして猿に引き止められ、舟に乗れなかったところ、その船が沈み猿のおかげで難をまぬがれたと云う話も当寺に伝わっている。
当寺は観音霊場として、江戸時代には山ノ手三十三所の第二番札所、現在は東京三十三所の第十九番札所となっている。
当時は通称〝さる寺〟と呼ばれ、さる寺縁起として『江戸名所図会』に「昔、境内に猿をつなぎて置きたりとて、今も世に猿寺と号く」と記されている。
また、元禄の頃四代目の住職・徳門和尚が渡船に乗ろうとして猿に引き止められ、舟に乗れなかったところ、その船が沈み猿のおかげで難をまぬがれたと云う話も当寺に伝わっている。
当寺は観音霊場として、江戸時代には山ノ手三十三所の第二番札所、現在は東京三十三所の第十九番札所となっている。
| 正式名称 | 蒼龍山松源寺 |
| 宗派 | 臨済宗妙心寺派 |
| 総本山 | 妙心寺(京都) |
| 宗祖 | 無相大師 |
| 本尊 | 釈迦如来・他に聖観音(出世観音) |
おすすめと特徴
さる寺と呼ばれる由来
むかしむかし、そのむかし、神楽坂に松源寺というお寺があり、そこの住職が、向島のお花見に招かれ、出かけることになりました。
その日は、とてものどかな春の日で、舟の渡し場までやって来た住職が、いざ乗ろうとすると、だれかがきもののすそを引っぱります。
「おや小猿さん、なにかご用かね」さらに歩こうとすると、小猿はまたきものを引っぱります。
そこに猿の飼い主がやってきました。
「これはこれはご住職、お出かけですか」「そういうあなたは武藏屋のご主人じゃありませんか」ここでしばし、立ちばなしとなりました。
気がつくと舟は出てしまい、ふたりはおいてきぼりです。「やや、しまった。舟をやりすごしてしまったぞ」
ところがその舟、川の中ほどまで進んだところで、突然ふいてきた大風と大波で、横倒しになってしまいました。
「やれやれ、小猿のおかげで助かったわい」「それもそのはず。その小猿は、ほれ、一年ほど前の…」武蔵屋がいうにはその小猿、まだ飼い主のいないころ、松源寺のけいだいでいじめられていたところを、住職が助けた小猿だったのです。
かんげきした住職は、武蔵屋から小猿をゆずってもらい、いつまでもなかよく暮らしたということです。
年中行事
春季彼岸会、盂蘭盆会、秋季彼岸会
松源寺の設備
本堂/山門/永代供養墓/墓所
 本堂 | 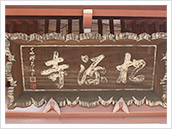 山門 |  永代供養墓 |  墓所 |
交通案内
- 所在地:東京都中野区上高田1-27-3
- 交通アクセス:
JR中央線東中野駅下車徒歩10分
地下鉄東西線落合駅下車徒歩10分
西武新宿線新井薬師駅下車徒歩10分